2023年12月18日
那国王の教室「黒田官兵衛孝高と千利休」+復元利休の菓子「ふの焼き」煎茶会
令和05年12月8日(金)。福岡市営地下鉄大濠公園駅5番出口集合。福岡城外堀西端角・かんぽ生命保険福岡サービスセンタービル横の潮見櫓再建現場前へ、、
下の橋御門横の伝潮見櫓との関係など説明。花見櫓として崇福寺へ移設されていた同櫓は、その後の解体工事の際に発見された棟札に「潮見櫓」とあり、その正体が確定されたなど、しゃべる。再建完成は令和7年の予定。なお伝潮見櫓は三の丸へ西側から登る裏御門の横に建つ「時櫓」だとされる。


覆屋手前に見える土がつめる枠は壁土を熟成させるためのプール。右は二階破風部分の部材組み
再建作業をつとめる大工さんによる手斧実演
大濠公園ボートハウス横へ移動。

奥村玉蘭・筑前名所図会にある「千賀浦古跡図」を参照に、現在の南当仁小学校敷地にあった黒田別邸鳥飼茶屋から見えた潮見櫓、武具櫓など、大濠公園・当時の草香江、または鳥飼潟から臨む福岡城を想像してもらう

筑前名所図会「千賀浦古跡図」中央小高く描かれた本丸上に三層の武具櫓。左手、丘陵が鳥飼潟・現在の大濠公園へ落ちようとするところに小さく潮見櫓が描かれている。潮見櫓の再建が完成し、かんぽ生命保険福岡サービスセンタービルがどいてくれれば、「千賀浦古跡図」が描かれた頃とおなじように、大濠公園側から同櫓がみえる

大濠公園中島を南側へ歩き皐月橋手前へ。東側、福岡市美術館方面を
望んでもらう。美術館の頭辺りに多聞櫓と天守台がわずかに顔を出す。築城時、初代長政が天守南の守りであると、重要性を強調して建設を急がせた武具櫓が再建されれば、多聞櫓の天守台の南上方に、伊予・松山城、陸奥・弘前城の天守閣クラスの規模をほこるその破風が輝いてみえる。
051208大濠公園歴史遠足レジュメ

そして、大濠公園日本庭園へ、、、

左.庭園広間入り口でその後の予定など/右.庭園表門

広間四景
那国王の教室:講演「黒田官兵衛孝高と千利休」
【要旨】
・岡谷繁実『名将言行録』、司馬遼太郎『播磨灘物語』にある、孝高が茶の湯を嫌悪したは事実か?
・「歌会・連歌会からの茶」、「藤原定家『詠歌大概』と茶湯」、「歌、古典文学につうじる孝高」
「近衛前久に歌を学ぶ、孝高祖父・明石宗和」などの事実と孝高の茶湯
・孝高参座の茶席「今井宗久茶湯日記抜書」/津田宗及 天正五年六月十一日条「宗及自会記」 天正十三年一月十六日条 /利休醒ケ井の会「今井宗久茶湯日記抜書」天正十五〔十四〕六月十三日条/利休野菊の会『宗凡茶湯日記他会記』天正十八年九月二十三日、などから考える
・天正十八年「極月四日」付、利休、孝高宛書状/孝高「茶の湯の記」/「宗湛日記」利休のふみカケテ・福岡城の会、などから考える
・大徳寺龍光院密庵席と孝高・大坂天満茶屋図から考える

詳細:051208講演「黒田官兵衛孝高と千利休」レジュメ参照
復元・利休の菓子「ふの焼き」とお茶
講演途中、休憩時間にお茶一煎目をサービス。光安茶舗「煎茶 千代結」100g¥3.000-使用

二煎目とあわせて「ふの焼き」を

「ふの焼き」の復元は江戸時代半ば、享保三年1719刊の菓子レシピ書『御前菓子秘伝抄』中にある製法を参考に博多区美野島のストライプスパン工房さんへ依頼。
ストライプスパン工房さんによると「ふの焼き」は「麩の焼き」だろうから、小麦たんぱく、グルテンを原料にするものとのこと。
つまり、「ふの焼き」は、小麦たんぱくを強化した焼き菓子。そこで、現代の小麦は、昔の小麦に比べるとグルテン含有量が多いため、特に、グルテンを強化せずに使用。一方で、製粉技術が当時より向上しているため、全粒粉を使用しました、とのこと。餡は、『御前菓子秘伝抄』「ふの焼き」の項目にある山椒味噌とクルミ。
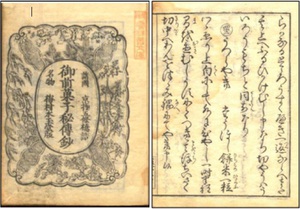
〜「御前菓子秘伝抄」・「ふの焼き」項より〜
ふのやき 小麦を、水にてしるくこね、ちいさき平銅ヒラアカヽネ鍋にくるみの油をぬり、少しつゝ入、うすくひろけ、やきて、むきくるみをきさみ、山椒味噌、白さたう、けしを、中へまきこめ申候。(東洋文庫・鈴木晋一『近世菓子製法集成』1所収)
〜利休の好み菓子〜
死の前年にあたる天正18年8月から翌19年閏正月までの間、利休は頻繁に茶会を行っています。その茶会の多くは『利休百会記』に記されていますが、88回中68回の茶会に「ふの焼」という菓子が使われています。当時の菓子は、「昆布」や「栗」や「饅頭」など素朴なものが多いのですが、「ふの焼」の使用回数はぬきんでています。そこから後世、「ふの焼」が利休好みの菓子と言われるようになりました。(「菓子資料室 虎屋文庫」より)
下の橋御門横の伝潮見櫓との関係など説明。花見櫓として崇福寺へ移設されていた同櫓は、その後の解体工事の際に発見された棟札に「潮見櫓」とあり、その正体が確定されたなど、しゃべる。再建完成は令和7年の予定。なお伝潮見櫓は三の丸へ西側から登る裏御門の横に建つ「時櫓」だとされる。


覆屋手前に見える土がつめる枠は壁土を熟成させるためのプール。右は二階破風部分の部材組み
再建作業をつとめる大工さんによる手斧実演
大濠公園ボートハウス横へ移動。

奥村玉蘭・筑前名所図会にある「千賀浦古跡図」を参照に、現在の南当仁小学校敷地にあった黒田別邸鳥飼茶屋から見えた潮見櫓、武具櫓など、大濠公園・当時の草香江、または鳥飼潟から臨む福岡城を想像してもらう

筑前名所図会「千賀浦古跡図」中央小高く描かれた本丸上に三層の武具櫓。左手、丘陵が鳥飼潟・現在の大濠公園へ落ちようとするところに小さく潮見櫓が描かれている。潮見櫓の再建が完成し、かんぽ生命保険福岡サービスセンタービルがどいてくれれば、「千賀浦古跡図」が描かれた頃とおなじように、大濠公園側から同櫓がみえる

大濠公園中島を南側へ歩き皐月橋手前へ。東側、福岡市美術館方面を
望んでもらう。美術館の頭辺りに多聞櫓と天守台がわずかに顔を出す。築城時、初代長政が天守南の守りであると、重要性を強調して建設を急がせた武具櫓が再建されれば、多聞櫓の天守台の南上方に、伊予・松山城、陸奥・弘前城の天守閣クラスの規模をほこるその破風が輝いてみえる。
051208大濠公園歴史遠足レジュメ

そして、大濠公園日本庭園へ、、、

左.庭園広間入り口でその後の予定など/右.庭園表門

広間四景
那国王の教室:講演「黒田官兵衛孝高と千利休」
【要旨】
・岡谷繁実『名将言行録』、司馬遼太郎『播磨灘物語』にある、孝高が茶の湯を嫌悪したは事実か?
・「歌会・連歌会からの茶」、「藤原定家『詠歌大概』と茶湯」、「歌、古典文学につうじる孝高」
「近衛前久に歌を学ぶ、孝高祖父・明石宗和」などの事実と孝高の茶湯
・孝高参座の茶席「今井宗久茶湯日記抜書」/津田宗及 天正五年六月十一日条「宗及自会記」 天正十三年一月十六日条 /利休醒ケ井の会「今井宗久茶湯日記抜書」天正十五〔十四〕六月十三日条/利休野菊の会『宗凡茶湯日記他会記』天正十八年九月二十三日、などから考える
・天正十八年「極月四日」付、利休、孝高宛書状/孝高「茶の湯の記」/「宗湛日記」利休のふみカケテ・福岡城の会、などから考える
・大徳寺龍光院密庵席と孝高・大坂天満茶屋図から考える

詳細:051208講演「黒田官兵衛孝高と千利休」レジュメ参照
復元・利休の菓子「ふの焼き」とお茶
講演途中、休憩時間にお茶一煎目をサービス。光安茶舗「煎茶 千代結」100g¥3.000-使用

二煎目とあわせて「ふの焼き」を

「ふの焼き」の復元は江戸時代半ば、享保三年1719刊の菓子レシピ書『御前菓子秘伝抄』中にある製法を参考に博多区美野島のストライプスパン工房さんへ依頼。
ストライプスパン工房さんによると「ふの焼き」は「麩の焼き」だろうから、小麦たんぱく、グルテンを原料にするものとのこと。
つまり、「ふの焼き」は、小麦たんぱくを強化した焼き菓子。そこで、現代の小麦は、昔の小麦に比べるとグルテン含有量が多いため、特に、グルテンを強化せずに使用。一方で、製粉技術が当時より向上しているため、全粒粉を使用しました、とのこと。餡は、『御前菓子秘伝抄』「ふの焼き」の項目にある山椒味噌とクルミ。
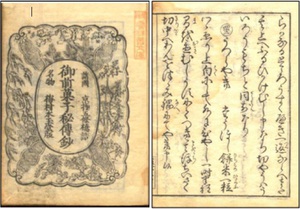
〜「御前菓子秘伝抄」・「ふの焼き」項より〜
ふのやき 小麦を、水にてしるくこね、ちいさき平銅ヒラアカヽネ鍋にくるみの油をぬり、少しつゝ入、うすくひろけ、やきて、むきくるみをきさみ、山椒味噌、白さたう、けしを、中へまきこめ申候。(東洋文庫・鈴木晋一『近世菓子製法集成』1所収)
〜利休の好み菓子〜
死の前年にあたる天正18年8月から翌19年閏正月までの間、利休は頻繁に茶会を行っています。その茶会の多くは『利休百会記』に記されていますが、88回中68回の茶会に「ふの焼」という菓子が使われています。当時の菓子は、「昆布」や「栗」や「饅頭」など素朴なものが多いのですが、「ふの焼」の使用回数はぬきんでています。そこから後世、「ふの焼」が利休好みの菓子と言われるようになりました。(「菓子資料室 虎屋文庫」より)



